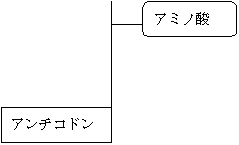くらしを問いなおす旅
NONE(なん)主催
遺伝子組み換え食品の講座
2003年6月7日
村上 悠
遺伝子とは何か? 歴史から見た遺伝
さて、遺伝子のお話をするということですが、まずは、遺伝について人間がどのように考えてきたのか、という事に焦点を当ててみたいと思います。
次いで、遺伝子についての科学的なお話をしようかと思います。
チラシにも書きましたが、遺伝子というものは決して難しいものではありません。DNAとかゲノムとかいった、専門用語に馴染みが無いので、ついつい敬遠してしまうのですが、しかし、その骨子は非常に単純です。今回は、専門用語については、新聞などに良く現れるもののみにして、遺伝の仕組みを中心にお話したいと思います。
では、まず遺伝というものを人間がどのように考えていったのかという歴史についてみていきます。
第1部「遺伝の歴史」
親から、子や孫に性質が伝わっていく「遺伝」。かえるの子はかえるになるということは、当たり前といえば当たり前ですが、それがなぜ起きるのかと問われれば、不思議なことでした。
遺伝に関わる記述には、紀元前4000年、つまり、今から6000年前の古代バビロニア(メソポタミア南部の王朝)の石版に、馬の頭やたてがみの特徴の伝わり方が数世代に渡って記録されていました。
しかし、これはどちらかというと実用的なものでした。遺伝を「学」として取り組んだのは、古代ギリシアの哲学者達でしょう。
その中で、ここではアリストテレスを取り上げましょう。
プラトンが、物の本質を「イデア」という別世界、真実の世界に求めたのに対し、物の本質は物自体であると考えたアリストテレスは、生物の綿密な観察を元に生物の本質に迫ろうとした人で、生物学の祖とも言えるでしょう。
さて、アリストテレスは人間の生殖を他の動物と比較し、精子を種、月経の血を畑の土のようなものとして捉えました。彼は、遺伝を担うものとして霊魂を挙げています。霊魂という名前はさておき、アリストテレスは遺伝の原因を粒子というよりもエネルギー的な実態の無い存在として捉えていたということが重要です。
アリストテレスのこの考え方は、カトリック神学に取り込まれ、以降、長い間影響を及ぼしていきます。
また、アリストテレスは目的論的な考え方を持っており、人間が人間のような形をしているのは、それが人間の本質だからであり、その本質を自然に目指そうとしているからと考えていました。つまり、アリストテレスにとって変異は異常であり全て淘汰されるものでした。こうしたアリストテレスにとって、それぞれの生物種につながりは無く、完全に分断されたものでした。
全ての物は、神が創ったものであり、悠久の過去から永劫の未来まで、そのままの姿であったし、あり続けると唱えていたカトリック神学にとっては、アリストテレスのこの考え方も都合のよいものでした。最も、こうしたアリストテレスの書物を保存し、その哲学を受け継いでいたのはイスラム帝国の科学者達であり、カトリック教会がこの考え方に触れるのは、十字軍によってイスラムの科学がヨーロッパに伝えられることによってだったというのは皮肉なものです。
この後、しばらくは遺伝学というよりも生物学での細胞に関する発見が重要となってきますが、それらを全て追っているときりが無いので、重要なものをかいつまんで説明します。
まず、8世紀頃アラブ人によってレンズが発明され、オランダのヤンセン親子が顕微鏡の原理を発見します。そして、イギリスのロバート・フックが顕微鏡を使って細胞を観察します(ヤンセン親子の顕微鏡とは原理が異なる)。さらに、細胞内に核が発見され、その後、全ての動植物が細胞からできている事が発見されます。その後、1831年からのダーウィンの進化論の研究(『種の起源』の発表は1859年)、1856年オーストリアの修道士メンデルによるエンドウ豆の交雑実験(発表は1865年)、1861年のパスツールによる自然発生説の否定がありました。
フックが細胞を最初に発見したのは1665年でしたが、全ての生物が細胞からなっているということが言われたのは1839年なので、全ての生物は細胞からなる。細胞(生物)は必ず細胞(生物)から生まれる。生物は進化する。生物の遺伝には規則性がある(→遺伝を担う専門の因子が存在する)。という、生物学の4大原則といえるものの発見が19世紀に集中して行われている事が分かります。これには、テクノロジーの進歩が重要だったといえるでしょう。
さて、ここでは遺伝学の父といわれるメンデルの研究についてもう少し深く見ていきたいと思います。
オーストリアの修道士であり、生物学者でもあったグレゴリオ・メンデルは、エンドウ豆の栽培中にエンドウ豆の遺伝には規則性があるのに気付きました。
そこでメンデルは、様々な性質を持つエンドウ豆を掛け合わせて雑種を作り、親の性質がどのように受け継がれていくのかを追っていきました。
メンデルは、34種類の異なった性質を持つエンドウで、7つの性質について調べました。ここでは、エンドウ豆のしわの有無の実験について説明します。
エンドウ豆には、豆にしわのあるものと無いものがあります。しわのある豆は、自家受粉すれば必ずしわのある豆になりますが、しわの無い豆は自家受粉してやってもしわのある豆が出来る事があります。メンデルは、エンドウ豆を、代々必ずしわの無い豆をつけるもの、もとはしわの無い豆だがしわのある豆をつけるもの、代々しわのある豆をつけるものの3つに分け、自家受粉及び他家受粉による交配実験を行いました。
すると、代々しわのある豆を作るものと、代々しわの無い豆を作るものを掛け合わせて作ったしわのある豆同士を掛け合わせると3:1の割合でしわのある豆と無い豆が生まれてきました。
また、代々しわのある豆を作るものと、代々しわの無い豆を作るものを掛け合わせると、必ずしわの無いものができるということが分かりました。
また、この豆のしわの遺伝には「花の色」や「背丈の高さ」という他の性質は無関係である事も確かめられました。
こうした現象は、アリストテレスの言うような「霊魂」による遺伝では説明がつきません。メンデルは、この実験結果を説明する為に以下のようなモデルを考えました。しわの無い豆を作らせる要素をA、しわのある豆を作らせる要素をaとし、えんどう豆は普通、要素を二つ持っていて(AA、aa、またはAa)、おしべの花粉とめしべの中にはそのうちの一つが渡される(A又はa)。そして、受粉によってそれぞれの要素が二つそろって次世代に受け継がれる。これを、メンデルの分離の法則といいます。
図1
|
分離の法則
AA
Aa aA aa |
優性の法則
Aa |
この他に、メンデルは、優性の法則、独立の法則の合わせて3つ、メンデルの遺伝の3法則を唱えました。
まずは、優性の法則です(図1の右)。
先述したように、遺伝で伝わる性質(遺伝形質)には勢力の強いものと弱いものがあるということです。人間で言えば、血液型のA型とB型が優性遺伝、O型が劣性遺伝となります。ところで、優性遺伝というなにやら優秀な性質をあらわすように感じます。しかし、このもととなった言葉は、“Dominant low”であり、dominantには「支配的な」という意味があります。つまり、この法則は「優勢」の法則であり、優性というのは誤訳っぽいのです。
そして、前述した、豆のしわの遺伝には「花の色」や「背丈の高さ」という他の性質は無関係ということが、独立の法則です。つまり、花の色にはBとb、背の高さにはCとcというそれぞれに別の要素が関係しているというのです。
メンデルは、この発見を雑誌に発表しましたが、学会からは相手にされませんでした。当時は、ダーウィンの進化論が注目を集めており、ダーウィンの進化論によれば生物に生じた細かな変化の積み重ねが進化の原因となっている事になっており、メンデルの「要素」を用いたモデルはダーウィンの考え方とは相容れないものでした。しかも、学会の重鎮だったカール・ネーゲリはダーウィンの進化論にしたがって研究を進めており、メンデルの成果を認めようとしませんでした。
メンデルは、まさにネーゲリが研究をしている「ミヤマコウゾリナ」という植物でも遺伝の法則が成り立つ事を証明しようとしましたが、ミヤマコウゾリナは単純なメンデルの法則に従わないため、メンデルは自分の理論を立証することを諦めてしまいました。この後、メンデルの発見は忘れられてしまいます。メンデルは失望のうちに1884年にその生涯を閉じました。
メンデルの遺伝の法則は、1900年にオランダのフーゴー・ド・フリース(突然変異説で有名)、ドイツのカール・コレンス、オーストリアのエリッヒ・チェマルクの3人がそれぞれ別々にメンデルの法則を再発見し、これによりメンデルは遺伝学の父と呼ばれるようになりました。因みに、コレンスはメンデルを冷たくあしらったネーゲリの弟子でした。
しかし、メンデルのこの結果は統計のスペシャリストであるフィッシャーに、数値があまりにもきれいであることを指摘されています。また、メンデル以前にも「優性の法則」「分離の法則」を示唆する研究がゲルトネルやヴィルモラン親子によって行われていましたが、彼等はこの発見を統計的に処理し、法則の発見にまでは至りませんでした。
メンデルの3法則は、この後の遺伝学において非常に重要なものであり、殊に生物学の研究に確率統計の手法を用いたことは非常に重要でした。
さて、先ほどのメンデルの遺伝法則の説明の際、遺伝子という言葉は使わず、要素という言葉を使いました。というのも、メンデルは遺伝という現象が起きる原因については興味を持ちませんでした。彼は、論文中では「遺伝子」という言葉は1度も使っていませんし、「遺伝因子」という言葉も1度使っただけでした。メンデルはエンドウ豆のかけ合わせにより、どのような性質が現れるかを数学的に表現することに重点をおいていたのでした。
遺伝子という用語を作ったのは、ヴィルヘルム・ヨハンセンという人でした。
さて、遺伝子という言葉ですが、これには「原子」「分子」と同じく「粒子」としてのイメージが盛り込まれています。1687年にニュートンが「プリンピキア」を発表し、1784年にラプラスがニュートン力学を完成させて以降、科学者達の多くが「質点(大きさを持たず、質量だけを持っている仮想粒子)の運動で、全てを理解する=力学的世界観」という考え方に惹かれていきます。化学の世界でのドルトンの原子説(1803年)も、この力学的世界観に則ったものでした。
1883年には、エルンスト・マッハによる力学的世界観への批判が出されていましたが、ヘルムホルツやケルビン卿などの大御所がこぞって力学的世界観を支持したこともあり、力学的世界観の影響力は非常に強かったのでした。当時は、物理学、殊に力学はもっとも完成された科学とされており、生物学も物理学のようになる事を目指していたのでした。メンデルは、論文中では遺伝子について言及する事はありませんでしたが、彼の頭の中でも「遺伝を担う粒」が受け継がれていく姿が思い浮かべられていたかもしれません。
閑話休題
この後、遺伝に関する研究は急速に進歩します。これには、メンデルによって遺伝の重要な考え方が提示された事もあるでしょうが、研究の為の様々なテクノロジーや知見の完成がこの時期に行われていった事も大きいでしょう。また、キリスト教会の影響が無くなり、社会の民主化が行われていった事もあり、自分の研究結果を自由に発表できるようになった事、英国王立科学協会のような科学振興を様々な国が行っていった事などがあるでしょう。
ここでは、重要なものをピックアップしていく事にします。
まずは、少し時代が戻りますが1871年、ドイツのミーシャが細胞の核を単離し、その中にある物質にヌクレインという名前を付けました。この、ヌクレインは今では遺伝子の本体として知られている核酸に、タンパク質が混じったものでした。この、ヌクレインからタンパク質を取り除く事に成功したのはリヒャルト・アルトマンでした(1889年)。核酸という名前を作ったのも、アルトマンです。
1902年にボヴェリーが遺伝子が核に含まれている事を実証。
1907年にサットンが、遺伝子が染色体上にあると唱える。
1914年、アメリカのトマス・ハント・モーガンがサットンの遺伝子の染色体説を証明。
1929年、レヴィンが、核酸にはDNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)があることを発見。
これらの発見により、遺伝子は核内に存在する染色体、ヌクレインにあることが分かりました。では、遺伝子の正体はなんなのでしょう。
先述したように、ヌクレインにはタンパク質と核酸が含まれています。遺伝子は、一体どちらなのか。
まず、遺伝子の正体として考えられたのはタンパク質の方でした。当時、タンパク質には非常に多くの種類が知られていたのに対し、核酸はアデニン・グアニン・シトシン・チミンという4種類しか知られていませんでした。(RNAでは、チミンの変わりにウラシルが使われる)
生物の多様な性質を担うのに、核酸は明らかに不十分なように見えたのでした。
しかし、1928年のグリフィスによる肺炎双球菌の実験と、それを受けた1944年にかけてのアヴェリーのさらに詳細な実験は、遺伝子の本体が核酸のDNAである事を示唆するものでした。
肺炎双球菌には、ネズミを殺すものと殺さないものがいるのですが、グリフィスは本来はネズミを殺さない菌に、すりつぶした(つまりは完全に死んでいる)ネズミを殺す菌を振り掛けると、ネズミを殺す菌に変わること(形質転換と言う)を発見しました。アヴェリーは、この実験を更に検証し、すりつぶしたネズミを殺す菌を遠心分離などで脂質や糖質を除き、更にはタンパク質分解酵素やRNA分解酵素を働かせても形質転換が起きる事から、「形質転換を起こす物質(アヴェリーは、形質転換を起こす物質=遺伝子という安易な結論を避けた)」が、DNAであるという結論に達しました。
しかし、当時は「遺伝子の本体はタンパク質である」という考え方が根強く、アヴェリーはかなり強固な反論にあいました。
またも閑話
1944年に、エルネスト・シュレディンガーが『生命とは何か』を出版します。シュレディンガーは、量子力学という物理学の世界で有名な人ですが、彼は自分の専門である量子力学の観点から「遺伝を担う本体は巨大分子でなくてはならない」という結論を導きました。この予言は、後に正しいことが証明されます。
閑話休題
さて、グリフィスとアヴェリーの研究以降も、多くの科学者は遺伝子の本体としてタンパク質を追い求めていました。しかし1952年、バクテリオファージというウィルスを研究していたハーシーとチェイスが、遺伝子の本体がDNAであることを証明します。
ウィルスは、タンパク質とDNAしか持たないもので、自分だけでは子孫を残す事は出来ません。ウィルスは他の生物の細胞に取り付いて、その細胞に自分の子供を作らせることで増殖するという奇妙な奴で、生物と無生物の境界に存在すると言われているものです。
さて、このウィルスが細胞に自分の子供を作らせる為には、自分の体を創る情報=遺伝子を細胞の中に入れ込んでやらなくてはいけません。
ところで、タンパク質とDNAにはそれぞれ特徴的な物質が含まれていて、タンパク質にはイオウが含まれていますが、DNAには無く、逆に、DNAには含まれているリンがタンパク質にはありません(最近になり、タンパク質のリン酸化がさまざまなタンパク質の働きやタンパク質による遺伝子の調節に関与していることがわかってきましたが)。※ウィルスの蛋白には無い。
そこで、ハーシーとチェイスは、タンパク質を放射線で目印をつけたイオウで、DNAを放射線で目印をつけたリンでそれぞれ標識し、タンパク質とDNAのどちらが細胞(この場合は大腸菌)に取り込まれるのかを調べました。その結果、細胞に取り込まれたのはDNAでした。
遺伝子の本体がDNAであることは、この時点でまず間違いがなくなりました。
同じ、1952年にアレキサンダー・ダウンスは、DNAの情報がRNAに読み取られ、その情報をもとにタンパク質が作られるというモデルを発表します。
このモデルの意味を理解するには、タンパク質というものを説明しなくてはいけないでしょう。
タンパク質と言えば、「肉」を思い浮かべる人が多いでしょう。実際、筋肉はもっとも多くのタンパク質が含まれている場所でもあります。しかし、タンパク質の役割はそれだけではありません。
私たちの身体の中では、生きていく為に様々な化学反応が起きていますが、その化学反応を担っているのがタンパク質からできた「酵素」というものです。
例えば、砂糖。これを、空気中で分解しようと思ったら、燃やしてやらなくてはなりません。しかし、私たちの身体は36℃という温度で、砂糖を完全に分解してそこからエネルギーを取り出しているのです。
タンパク質の英語「プロテイン」は、ギリシア語で「1番目のもの」という意味があります。私たちが生きているのは、まさにタンパク質が活躍しているからなのです。
※現在では、RNAも生理化学反応に関与しているらしいといわれている。
この、タンパク質はアミノ酸という物質がネックレスのようにつながり、それが複雑にからんでダマのようになっています。それぞれのタンパク質は、特徴的なアミノ酸の順番があり、正しい順番でアミノ酸が繋がっていかないといけません。
ダウンスは、アミノ酸配列の順序を決めている原因をDNAに求め、それがRNAに仲介されてタンパク質になっていくと考えたのでした(タンパク質の合成にRNAが関係している事は以前から考えられていた)。
しかし、DNAにはアデニン(A)、シトシン(C)、チミン(T)、グアニン(G)という4種類の塩基しかないのに対し、タンパク質を作っているアミノ酸には20種類のものがあります。この問題を解決する為に、ダウンスは3つの塩基でひとつのアミノ酸を示す暗号を作っているという考え方を打ち出しました(これを、現在ではコドンと呼んでいます)。4種類の塩基を3つつなげる組み合わせは、4×4×4=64通りになります。20種類のアミノ酸を決めるのに十分となります(二つでは、4×4=16でまだ足りない)。しかし、アミノ酸は20種類、それに対し暗号は64種類もあるとはどういうことでしょう。残り44種類は使われていないのでしょうか?ダウンスは、そうではなくて、ひとつのアミノ酸を示す暗号が数種類あると考えました。
ダウンスの考え方は、細かい点では間違っている点もありましたが、大筋では合っているものでした。
そして、1953年ワトソンとクリックがDNAはアデニンとチミン、シトシンとグアニンがそれぞれ結びついて作られる、2重らせんの鎖からなるというモデルを提唱。また、彼らはDNAの情報が子供に伝わるときには、二本の鎖がいったんほどけ、それぞれの鎖が鋳型となって二つの二本鎖DNAが作られるという半保存的複製説も打ち出しました。これらは両方とも、正しいことが後に証明されます。
これ以降、生物学はさらにものすごい速度で進歩していきます。これ以降の歴史を追っていくことはかえって混乱を招くでしょうから、遺伝の歴史はここまでにして、現在分かっている遺伝子の知識についてお話したいと思います。
第2部「現在分かっている遺伝子の姿」
生物の身体は、細胞という単位から出来ています。生物の性質を次世代に伝えていく遺伝子は、DNAという物質から出来ています。真核生物では、DNAは核の中にしまわれています。この、DNAは非常に巨大な分子で、人間の場合、ひとつの細胞のDNAを全てつなげると2mにもなります。細胞の大きさは、せいぜい0.15mm程度ですし、核はその中にあるわけですから、さらに小さなものになります。DNAは、非常にコンパクトな形にまとめられています。
さて、DNAの役割は基本的に二つあります。ひとつは、遺伝子の本体の名が示すように次世代に性質を伝える事です。もうひとつは、普段の生活で必要なタンパク質を作る設計図となる事です。
単細胞生物を例に解説しておきましょう。
まず、前者ですがこれは細胞分裂を行う時に行われます。歴史の所でいったような、半保存的複製が行われて、2つになり、分裂するそれぞれの細胞に受け継がれていきます。さて、細胞分裂する際には分裂したそれぞれの細胞にきちんと必要な情報全てが伝わる必要があります。そのために、細胞は分裂する際に染色体というものを作ります。普段は、もやもやとしていて形を持たない核酸ですが、分裂の時にはまとまって形を作り、染色体というものになります。引越しの時に、荷物をまとめてダンボールに入れるのと同じです。
次に、タンパク質を作る過程ですが、この場合は二本鎖DNAの読み取る部分だけがほどけ、その情報が一定の方向に従って、RNAに読み取られます。そのRNAは、細胞内のリボソームというところに持っていかれます。リボソームには、このRNAを保持する部分が存在し、DNAの情報を読み取ってきたRNAをつかまえます。
|
tRN |
さて、ここでひとつ重要な分子について説明します。その名をトランスファーRNA(tRNA)とよび、右図のような形をしています。これもRNAなのですが、先ほどのDNAの情報を読み取ってくるRNAとは形も役割も全く違っています。
右図のRNAをtRNAと呼ぶのに対し、先ほどのRNAはDNAの情報を伝える役割をするので、メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれています。
さて、tRNAの役割ですが、RNAもDNAと同じく相補的な塩基対を作ります。tRNAは、mRNAのコドンに対応する3つの塩基(アンチコドン)を持つ場所があります。また、それぞれのtRNAは、持っているアンチコドンによって特有のアミノ酸を結合します。
tRNAは、mRNAの塩基のならびにしたがってアミノ酸を並べていく役割を果たします。
これらのアミノ酸はリボソームの上で互いに連結され、タンパク質になります。tRNAのトランスファーとは「転移」という意味で、核酸の塩基配列をアミノ酸配列に転移するからtRNAと呼ばれています。
こうして、DNAの情報はタンパク質に読み取られ、生物の様々な性質を発現することになります。
つまり、DNA→mRNA→tRNA→たんぱく質という順に情報が伝達されるのです。ここから分かるように、ひとつのタンパク質には専用のDNAの情報(塩基配列)があります。この、シンプルなリニア(直線的)な系は、生物のひとつの性質を、ひとつの遺伝子に帰着させようとするものであり、この単純な考え方こそ、多くの科学者を惹きつける原因なのでしょう。
とはいえ、実際にはそんなに単純ではありません。例えば、先ほど書いた「DNA→mRNA→tRNA→たんぱく質」という流れも、何十段階もの化学反応が起きており、また、必要なタンパク質を必要な時に作るためには、細胞内での複雑な情報のやり取りがあります。
フランシス・クリックは遺伝子の情報が読み取られる流れは「DNA→mRNA→tRNA→たんぱく質」という一方向のみだという「セントラルドグマ」という考え方を発表しました。そこから、最近では遺伝子が生物の全てを決定しているような事を言われていますが、遺伝子はあくまで設計図に過ぎません。
生命にとって必要なものを、必要な時に、必要なだけ作るという為には、細胞の他の物質(基本的には酵素蛋白)との緊密な連携が必要です。なにしろ、DNAの情報からmRNAを作るのも、tRNAに必要なアミノ酸をくっつけるのも全て酵素が行っているのです。DNAが全てというのはあまりに誇張といえるでしょう。
さて、ではこうした遺伝子とタンパク質の連携作業はどのようにして進化してきたのでしょう。偶然?それとも神の意志なのでしょうか?実は、遺伝子の進化の過程はまだよく分かっていません。今の所わかっている所だけを説明しましょう。
しかし、その前に真核生物と原核生物のDNAの違いを説明しておきましょう。
生物学者たちは長い間、全ての生物は基本的に同じメカニズムで理解できると思っていました。大腸菌のような細菌のDNAも、人間のDNAも量的な違い以外は同じだと考えていたのです。
しかし、1977年にギルバートがマウスの遺伝子が、DNA上では飛び飛びに存在している事を発見。同年に、利根川との共同研究の論文の中で遺伝子の必要な部分の間にある部分に「イントロン」という名前を付けます。
この、イントロンはmRNAに読み取られはするものの、その後に取り除かれ(これをスプライシングと呼ぶ)、その後に、リボソームに運ばれていきます。
現在では、このイントロンは全ての真核細胞のDNAに存在しているが、細菌類には存在していない事がわかっています。しかし、当時は「DNAの仕組みは、全ての生物に共通だ」と考えられていた為、この発見は衝撃的でした。
しかし、イントロンのような無用なものがどうして存在するのでしょう?
実は、イントロンは完全に無用というのではありません。例えば、スプライシングする場所を変える事で、同じDNA上の場所から、2種類の活性の違う酵素を作る。という使い方が知られていますし、最近ではイントロンの配列が神経伝達物質の伝わり方に影響を与えるのではないかという報告もあります。また、使われない配列を持ち、そこに突然変異を起こすことによって、進化の挑戦を行う事が出来ます。
しかし、人間ではイントロンは全DNAのうちの97%にまで達しており、どんな理由があるにせよ多すぎる気がします。
イントロンを調べてみると、偽遺伝子と呼ばれる以前は使われていたはずだが、現在では突然変異を起こして使えなくなった遺伝子や、もとはウィルスの遺伝子だったものが不活性化されて取り込まれたものが見つかり、「もとは、遺伝子はシンプルな配列だったが、進化の過程でイントロンが積み重なっていった。」という考えがあります。
しかし、最初に出来た遺伝子に全く無駄がなかったというのには無理がある。「原始的な生物にはイントロンが存在したが、分裂を繰り返し、子孫の数で勝負する細菌類のような生物ではイントロンはお荷物になるのでイントロンをなくしていった。」という考えもあります。
それを踏まえて、遺伝子の進化について現時点で分かっていることをお話してみましょう。
最初の生命体は、38億年前頃に生まれ、自己複製するRNAだったと考えられています。つまり、自分と同じ塩基配列を持つRNAを自分自身で作ることが出来るものがいた。次いで、RNAとタンパク質が協同作業を行うようになり、RNAを複製するのがタンパク質によって行われるようになっていきます。
しかし、RNAは分解されやすく、長期間安定して遺伝情報を伝えるには不向きでした。そして、そのうちに分子としてより安定している、DNAが使われるようになっていきました。現在では、RNAを遺伝子として使っているのは一部のウィルスのみです。
こうして、原始的なコモノートと呼ばれる生き物たちが生まれてきました。そして約18億年前、ここから、まず原核生物(真正細菌、一般的に細菌と呼ばれているもの)の仲間が分化します。細菌は、より速い分裂を目指すため、無駄な配列であるイントロンを捨てていき、必要なDNA配列のみを残していきます。一方、次に、約15億年前に後生細菌(古細菌とも呼ばれる。メタン菌が有名)と、真核生物が分化していきます。真核生物は、原核生物と古細菌が共生する事で生まれたといわれていますが、真核生物はイントロンをより複雑な構造を作るために利用する方向に進化しました。
これが、現在わかっている所です。
これ以外にも、DNAのアデニン・チミンとグアニン・シトシンの量の比や、RNAエディティング、遺伝暗号の進化など面白い話は尽きないのですが、これ以上やると詰め込みすぎになるでしょうからここまでにしましょう。
第3部「用語の説明」
![]() さて、なにか手順前後のような気もしますが、最近、新聞やテレビなどでよく出てくる遺伝子に関する用語、このうちで、必ず使い分けておきたい4つ、染色体、DNAとRNA、ゲノム、遺伝子について説明しておきましょう。
さて、なにか手順前後のような気もしますが、最近、新聞やテレビなどでよく出てくる遺伝子に関する用語、このうちで、必ず使い分けておきたい4つ、染色体、DNAとRNA、ゲノム、遺伝子について説明しておきましょう。
染色体については、細胞分裂のところで説明しましたが、右図のような棒状のものを見たことがあると思います。
有性生殖(オスとメスで子供を作ること)を行う生物では、同じ役割をする染色体を2本ずつ持っています。お分かりと思いますが、父親と母親から一本ずつ受け継ぐのです。人間では、23種類の染色体を2本ずつ46本持っています。
染色体は普段は存在せず、細胞分裂のときにのみ、遺伝子を整理する為に姿をあらわします。
次はDNA・RNAです。歴史の所で解説したように、まずは細胞の核の中から核酸が発見され、次いで、核酸にはDNAとRNAがあることが分かりました。遺伝子として使われているのは、ほとんどDNAです。まぁ、遺伝子の原料がDNAだと考えていただければよいと思います。RNAは、DNAの情報からタンパク質を作るのに使われ(RNAウィルスのみは例外)、基本的には使い捨てです(無論、リサイクルはされますが)。
ゲノムとは、一つの生物が持つDNAの全情報、全塩基配列です。最近、ヒトゲノムが解読終了したということで、よく聞く言葉になってきたのではないでしょうか?人間の塩基配列は、約30億塩基対といわれ、ATGCの4種類の文字が30億あります。
さて、次は遺伝子の定義ですが、これは非常にややこしいのです。というのも、真核生物の場合には、先ほど述べたイントロンという部分があり、タンパク質のアミノ酸配列を決めているDNAの情報が、無意味な文字列によって寸断されているからです。また、大腸菌のようなイントロンを持たない生物でも、DNAの塩基配列の一部が重って使われている事があります。
現在では、分子生物学では「遺伝子とは、タンパク質に翻訳されるDNAの塩基配列」と定義しています。
第4部「遺伝子が全てなのか?」
血は水よりも濃い。
というのは、昔から言われてきました。しかし、心理学の研究などから、人間の行動については遺伝的な影響よりも、後天的な学習の影響の方が大きい。といわれるようになってきていました。また、学習重視の考え方が、民主主義的な価値観に合致していた事も大きいでしょう。
しかし、最近の遺伝子に関する知識や、テクノロジーの進歩からか、「血統」が科学的な装いで再登場してきたように見えます。糖尿病になりやすい、癌になりやすい、うつ病になりやすい、冒険を好むなどといった「遺伝子」が、次々と報告されています。
しかし、これらのほとんどが、科学的なメカニズムが解明されているわけではなく、「癌になりやすい一族で、癌になった人とならなかった人のDNAを比べてみたところ、癌になった人だけに特有な配列があった。(あるいは逆に、特有な配列が無かった)」という、疫学的(統計的)なもので、後になって間違いだったことが報告される事もよくあります。
しかし、マスコミは「発見された」ことは報道しても、「発見が間違いだった」ことは報道しません。これによって、あたかも遺伝子の研究が順風満帆に言っているような印象を与えているのではないでしょうか。
また、ヒトゲノム解析の終了は、ヒトの遺伝子について科学が解明してしまったような印象を与えているのではないでしょうか。
しかし、先ほど述べたように、ゲノムとは「生物の全塩基配列」であり、要はどんな文字があるのかが全部分かっただけです。たとえば、「ある古代文明の文書(石版に彫られたもの)の完全版が発掘された状態」に過ぎないのです。
この、全文字列のどこが「遺伝子」となっているのか。については、まだ、部分的に分かっているに過ぎません。文字の意味を読み解く作業はこれからなのです。
確かに、ヒトは遺伝子のかなりの部分について解明してきました。しかし、まだ分かっていない部分も多く、しかも、そのわかっていない所こそ様々な生物の個性であったりします。
そして、何より問題なのは遺伝子が全てを決めているのではないということ。

これは、『Nature 2002年2月14日号』に発表されて大きな話題となった、クローンネコの写真です。(a)の写真が、DNAを提供した親ネコで、(b)の大きい方のネコが、子宮を提供した「産みの親」、(b)の小さい方が生まれたクローンネコです。
つまり、(b)の子猫が、(a)のクローンなのです。クローンは、DNAの配列は完全に同じです。しかし、一見して分かるように、2匹のネコの毛の色は違っています。毛の色ですら、遺伝子が全てを決定しているわけではありません。
また、ミツバチの幼虫が、将来、働きバチになるか、女王バチになるかは遺伝子によっては決まっておらず、与えられる餌によって決まるという話は、最近の「ローヤルゼリーブーム」で聞いた人もいるかもしれません。女王バチも、働きバチも遺伝子は全く一緒なのです。
遺伝子は、生命の設計図。非常に大切ではありますが、それだけで生命の全てが決まるわけではないのです。
第5部「第2回へのつなぎとして」
科学はまだ、遺伝子の全てを解明したわけではない。
遺伝子が、生命の特徴を全て決めているわけではない。
この二つは、遺伝子組み換え技術の大きな問題点としてのしかかっています。遺伝子の知識が完璧でない以上、遺伝子組み換え技術が完璧である事は有り得ません。
次回は、遺伝子組み換え技術の基本的な知識と、遺伝子に関する知識の不備からくる遺伝子組み換え技術の問題点、さらには、遺伝子組み換え技術を進めようとしている「力」についてお話したいと思います。
文・村上 悠
参考webページ
西脇研究室 http://www.phsc.jp/~nishiwaki/
森田保久の高校生物関係の部屋 http://village.infoweb.ne.jp/~yasuhisa/hisa1.htm
いきものの世界 http://big.big.or.jp/~mastakeu/
遺伝学電子博物館 http://www.nig.ac.jp/museum/
堀 寛(ほりひろし)のホームページ http://biol1.bio.nagoya-u.ac.jp:8001/~hori/hori.html
DNA研究の歴史 http://sapporo.cool.ne.jp/sakk/DNAnenpy.htm
化学・生化学電子図書館 http://www.sc.kochi-u.ac.jp/~tatukawa/edu/semc3/
NS遺伝子研究室 http://web.wtez.net/n/s/ns54007/
Bio-Resource Network Symposium ’99 http://bio.tokyo.jst.go.jp/symposium/
参考文献
『分子生物学の基礎 第2版 David Freifelder/George
M.Malacinski・著 川喜田正夫・訳
(東京科学同人)』
『精神と物質 立花隆/利根川進・著 (文藝春秋社)』
『古代ギリシアの思想 山川偉也・著 (講談社学術文庫)』
『生物学の倫理〜分子・細胞・進化〜 矢原一郎・著 (岩波書店)』
『遺伝暗号の起源と進化 大澤省三・著 渡辺公綱/上田卓也/大濱武・訳 (共立出版)』
『重力と力学世界〜古典としての古典力学〜 山本義隆・著 (現代数学社)』
『マッハとニーチェ〜世紀転換期思想史〜 木田元・著 (新書館)』
『Nature 2002年2月14日号』
『Newton 2003年7月号 (ニュートン プレス)』